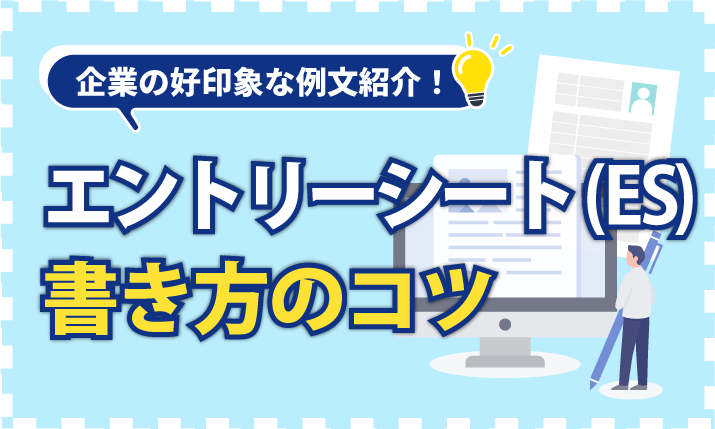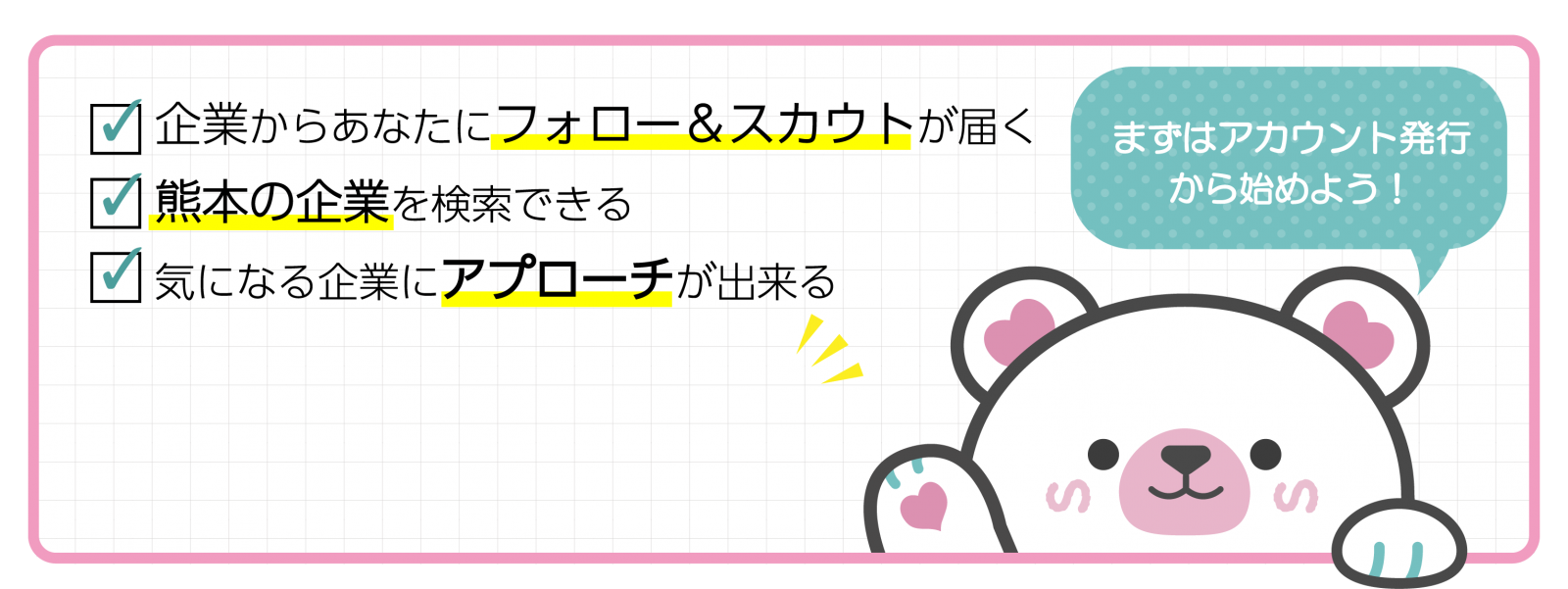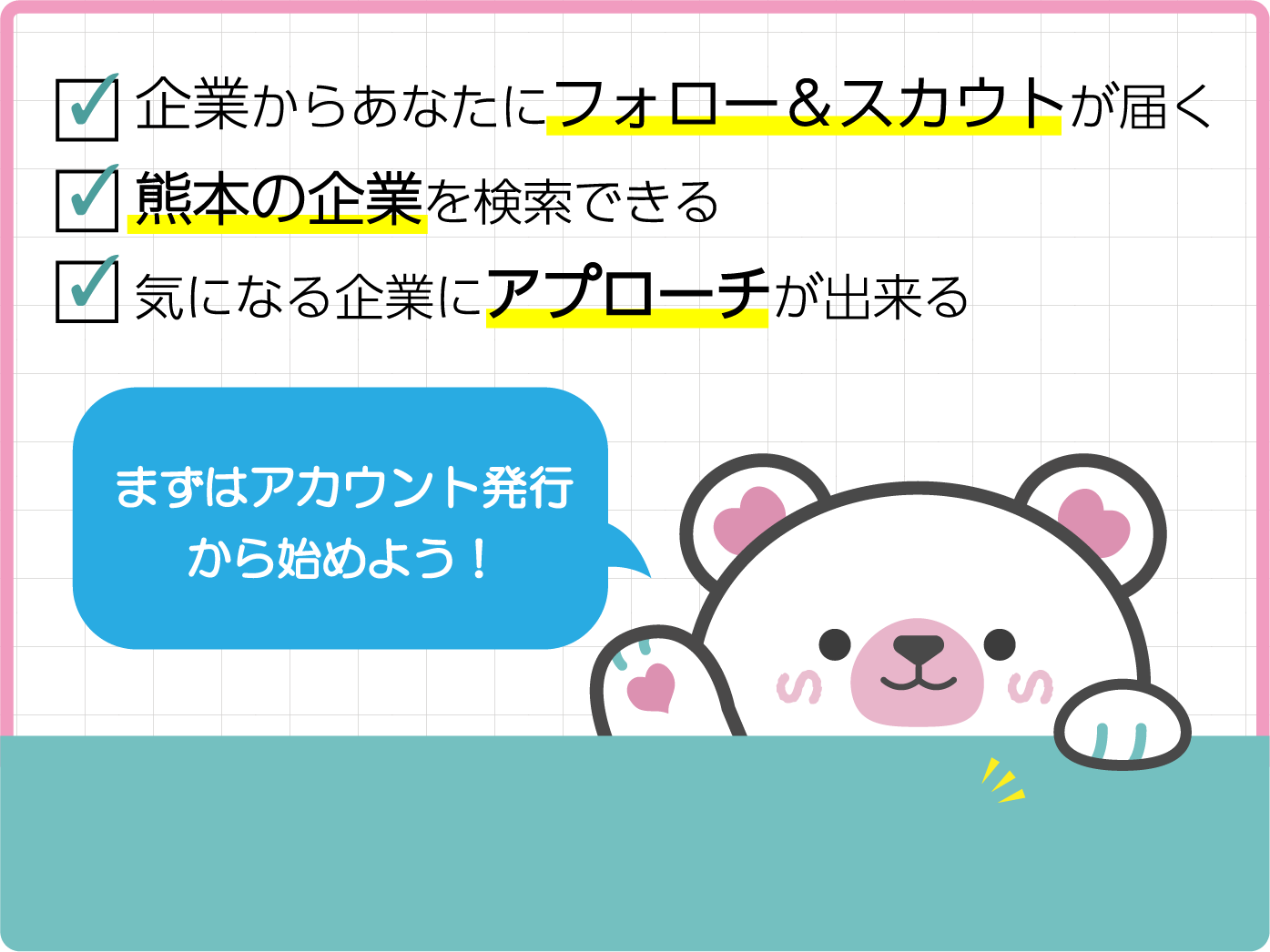エントリーシートは就活生の第一印象を決める重要な応募書類!
企業には連日、多くの就活生から応募が集まってくるわけですが、その中で採用担当者の印象に残るエントリーシートを書くにはどのようなことに気をつけたらよいでしょうか?
書き方のコツを例文とともに紹介していきます!
2. 企業が見ているポイントは?
3. 採用担当者に評価されるESを書くには?
4. エントリーシート(ES)を書く時の注意点
5. よく聞かれる質問と例文
6. まとめ
5. スカウト型サイト「就活応縁くまもと」は企業の情報が盛りだくさん!
エントリーシート(ES)とは?

エントリーシートは、企業が就活生の人柄や熱意を知るための手がかりとなる書類です。各企業はそれぞれ独自のフォーマットを用意しており、Web上で入力するものや、手書きして郵送するものなどがあります。フォーマットは企業の採用ページや就活サイトなどで入手できます。
エントリーシートの提出時期は、採用情報の公開が始まる3・4・5月ごろにかけてが一般的です。採用選考に応募する時だけでなく、インターンシップへの参加を申し込む際にも提出が求められることがあります。
エントリーシート(ES)の用途と重要性
エントリーシートは単なる応募用紙ではありません。企業の採用活動の中でどのような目的で使われているかを知れば、その重要性についてより深く理解できるでしょう。
用途①足切りの判断材料
エントリーシートを提出すれば本選考に進めるという企業もある一方で、書類選考的な意味を持たせ、足切りの判断材料とする企業もあります。特に応募者多数の企業は、全員に対して面接を行うのは工数がかかります。採用期間も限られているため、エントリーシートの段階で面接する人を絞らなければなりません。エントリーシートが通過しなければ面接や筆記試験など、次の段階に進むことはできません。 就活生としては採用担当者が読みやすいと思ってもらえるエントリーシートを作成することが重要になります。
用途②面接時の参考資料
また、採用担当者は、スムーズに面接を進めるために、事前資料としてエントリーシートを読み込んでおく場合があります。 そのため、エントリシートは面接時に参考資料として、面接官の手元に置かれる場合があります。記載の内容が事実と相違ないか確認するとともに、具体的な説明を求めることで、就活生の人となりや価値観を理解します。エントリーシートを書く際に、自分の考えをきちんと整理することができれば、それが面接対策にも繋がります。就活生は、エントリーシートを書く段階で、自分の考えをきちんと整理し、面接対策にも繋げるようにしましょう。
履歴書との違いは?
エントリーシートと履歴書どちらも重要な応募書類ですが、それぞれが求められている内容は
- エントリーシート=人柄、強み、熱意などの “内面的な部分”
- 履歴書=住所、連絡先、経歴、資格などの “基本情報や事実”
大雑把にこのような表現で区別ができるかと思います。
少し厄介なのが、エントリーシートと履歴書の質問項目が重複している場合です。例えば、両方で志望動機について聞かれるなんてケースも多々あります。この時、「同じことを書いてもいいの?」と思うかもしれませんが、エントリーシートと履歴書で内容が重複していても問題ありません。「履歴書はより簡潔に」、「エントリーシートはより細かく、具体的に」という風に違いをつけて書き分けましょう
企業が見ているポイントは?

各企業の採用担当者は、エントリーシートを通して就活生の何を見ているのでしょうか。どのようなポイントを踏まえれば評価されやすいのか紹介していきます。
①会社への熱意・志望度の高さ
当たり前のことですが、企業は確実に入社してくれそうな、熱意の感じられる学生を採用したいと考えています。企業や業界に興味を持った具体的なエピソードや、業界研究・企業研究で知った最新の動向に対する考えなどをきちんと示しているエントリーシートは評価されるでしょう。反対に、誤字脱字や汚字が目立ったり、ありきたりな表現を使い回したりしているエントリーシートは雑な印象を与えてしまい、書類選考で落とされてしまいます。
②分かりやすく伝える文章力
面接では対話力が見られますが、エントリーシートでは文章力が見られます。企画書や報告書など、ビジネスシーンでは文書でのやり取りが頻繁に行われますが、この時、「誰が読んでも短時間で理解できる、簡潔で分かりやすい文章」が求められます。自分の意図を的確に伝えられなければ、業務で混乱を招いてしまうでしょう。このため、文章力はビジネスパーソンにとって欠かせないスキルです。
③企業側が求める人材像にあっているか
採用においてどんな人物を求めているかは、企業によって異なります。業種だけではなく社風もさまざまなのです。例えば現状維持のためにコツコツ努力できることは素晴らしいことですが、「新しくどんどん開拓していく」という社風の企業に対してはあまりアピールポイントにならない可能性があります。そのため企業研究をしっかり行い、求める人材に合わせた自己PRを行うことが大切です。
③入社後の活躍を期待できるか
エントリーシートでは、「入社後に活躍できるような能力があるか」「意欲的に働き続けてくれるか」といったポイントを測られます。「特別な経験や資格がない…」という人であっても、「今後、どのように努力をしていくか」「どんな目標を達成していきたいのか」といった明確なビジョンをアピールすることができれば、評価につながります。
④その企業にどんな魅力を感じているのか
その企業にどんな魅力を感じているかで就活生の価値観を判断することができます。企業側の視点でいうと、大事にしているミッションや今後向かっていきたい方向と、就活生がマッチしていると判断した場合、一緒に働けると判断されます。そのため、企業の魅力に関しては、就活生が自由に書くのではなく、「企業が押さえて欲しそうなポイント」を見つけて書くことが重要になります。
⑤モチベーションは十分にあるか
その企業に限らず、働くこと全体へのモチベーションがあるかどうかもエントリーシートから判断されます。例えば、誤字脱字が多い、期限に遅れている、丁寧な字で書かれていないという場合は、就活や働くことへのモチベーションがないと判断されてしまいます。将来を決める大事な書類であるエントリーシート、丁寧に取り組んでくださいね。
採用担当者に評価されるESを書くには?

採用担当者は限られた時間の中で、送られてきた全てのエントリーシートに目を通さなくてはなりません。自分のエントリーシートを最後まできちんと読んでもらうためには、読み手を意識した読みやすい文章である必要があります。
基本的な書き方のルール
ビジネスの場ではスキルや能力に関わらず、「丁寧な人」「ルールを守る人」は評価されます。エントリーシートを提出する際も、最低限のマナーを忘れてはいけません。
- 誤字脱字がないか
- 文字の読みやすさ(綺麗さ、大きさ、空白)
- 全ての質問に答えているか(空欄はないか)
- 規定の文字数に達しているか
文章を書くのが苦手という人でも、これらは意識しやすいポイントだと思います。また、企業ごとにルールが定められている場合もありますので、エントリーシートの指示はよく読んでおくようにしましょう。
下準備(自己分析、企業・業界研究)が重要
エントリーシートを書く際には下準備が重要になります。
具体的には以下の3つとなります。
・企業研究:企業の業界における立ち位置、ミッション、これから目指す方向を確認
・業界研究:業界全体の現状課題、将来について研究
この段階では、エントリーシートに書くかどうかに関係なく、思いついたことをどんどん書いていきましょう。
企業に合わせてアピールポイントを絞る
企業研究を終え、自分の活動を書き出したら、エントリーシート に書く内容を考えます。
サークル、アルバイト、学業など、就活生の皆さんはさまざまな活動を行ってきたかと思います。
ですが、一貫性を高め、自分の強みをアピールするには、書く内容を絞ることが大切です。
自分を売り込むために、アピールポイントやエピソードをたくさん詰め込みすぎてしまうと、伝えたいことがぼやけてしまいます。いろんな方向に散らばった話題を一貫性のある文章にまとめるのは至難の業。
記入スペースや文字数には限りがあるため、一つ一つのエピソードの内容が薄くなり、具体性にも欠けてしまいます。
どのようにして絞るのかは、企業のミッションやこれから目指す方向によって変わってきます。
やみくもにアピールするのではなく、「応募先企業がどんな人材を求めているか」を理解し、一番刺さりそうな話題を絞り込むよう心がけましょう。
メモアプリやWordなどへの下書きを行う
いよいよ書き始めますが、Web・手書きに限らずいきなり書かずにまずは下書きを行いましょう。
思いつくがままに書いてしまうと、どうしても主語述語にねじれが出てしまったり、構成が整っていなかったり、ということが起こります。手書きだと修正ペンが印象を悪くしてしまうのはもちろん、Webでも記入欄が狭いと、違和感に気付きにくくなってしまいます。メモアプリ、Wordどちらでもよいのでまずは下書きをしておきましょう。手書きの場合は、可能であればエントリーシートをコピーして、どのような文字の大きさであれば全て書ききることができるのか、チェックをしておくと良いでしょう。
誤字脱字・表現のチェック
下書きを書き終えたら、基本的な誤字脱字や表記揺れ、主語述語のねじれなどがないかをチェックしましょう。
最近は、ChatGPTやClaude 3など、AIで文章を添削してもらうことができるので、是非活用してください。(※ただし最初からAIに書かせたものを提出するのはNGです。表現の参考にするぐらいなら良いのですが、AIが書いた文章は雰囲気で分かってしまいます。)
他人にフィードバックをもらう
書き終えたら、第三者の目から文章を読んでもらい、フィードバックをもらうことが大切です。
可能であれば、社会人経験のある方(ご家族や先輩など)に見てもらうと良いでしょう。
社会人と学生ではやはり見ている景色が違いますから、社会人の視点からのチェックは貴重なものです。
難しければ、信頼のおける友達などに、文章の読みやすさなどをチェックをお願いしましょう。
友達も就活生であれば、お互いチェックし合って、書き方を学べると良いかもしれません
エントリーシート(ES)を書く時の注意点

採用担当者は限られた時間の中で、送られてきた全てのエントリーシートに目を通さなくてはなりません。自分のエントリーシートを最後まできちんと読んでもらうためには、読み手を意識した読みやすい文章である必要があります。
です、ます調を用いる
エントリーシートは企業への応募書類であり、ビジネス文書の一種です。そのため、適切な言葉遣いと丁寧な表現が求められます。丁寧語の「です・ます調」を用い、常に敬語を心がけましょう。
質問に的確に答える
多く見られるミスの一つに、「的外れな答えを書いてしまう」というものがあります。その中でも、「質問を理解しているのに、自分の主張が空回りしている」というケースが多く見られます。
このようなミスを防ぐ対策の一つは、“結論を最初に書くこと”。
結論の前に自分の考えを長々と書いているうちに話が逸れてしてしまう人は多いです。「最初の一文できちんと質問に答える」→「二文目以降で自由に根拠や考えを述べる」という形をルール化してみましょう。
読みやすい構成にする
読み手が理解しやすいよう、エントリーシートは論理的な構成を意識しましょう。
【結論→エピソード→まとめ】の順で書くのがおすすめです。
最初に主張や結論を示し、次にその根拠となるエピソードを具体例として挙げ、最後に要約してまとめる、という構成がわかりやすいでしょう。
型を作っておけば、複数の企業に応募する時にエントリーシート作成が少し楽になると言うメリットもあります。
改行できない場合は記号を用いる
エントリーシートをWeb上で入力する場合、改行ができず1行の文字数制限があることがあります。その際は以下の方法で分かりやすさを確保しましょう。
・箇条書きの項目は① や (1) などの記号を用いて区切る
・改行を行うときは、■の記号などで適宜区切る
可能な限り具体性を持たせる
客観性と説得力を高めるため、エピソードや事例には具体的な内容を盛り込みましょう。
・具体的な数値や実績 (例: イベント企画で100人集めた、居酒屋で売上10%UPした、など)
・第三者からの評価やコメント(例:アルバイトでお客様より「〇〇」のお言葉を頂いた。)
抽象的な表現は避け、読み手が状況を想像しやすいよう具体性を持たせることが重要です。
よく聞かれる質問と例文

この章では、エントリーシートでよく聞かれる質問と、答えの例文を紹介していきます。
どの質問の答えにも共通するのが、「結論(答え)から書き始め、具体的なエピソードで肉付けしていく」こと。
あくまで書き方の一例ですが、ぜひ参考にしてみてください。
【例文】自己PR
①私の強みは、グループ内の人間関係を円滑にする力です。
②大学のゼミ内で、日頃からいがみ合っていた友人同士の仲を修復することに成功しました。
③ゼミでグループ発表を行った際、元々仲が良くなかった友人同士の意見が食い違い、雰囲気が今までにないくらい悪くなってしまったことがありました。このままでは今後のゼミの活動に支障をきたすと思い、それぞれに「相手の何が気に入らないのか」「どうしたら相手を許せるのか」を聞きました。
仲違いは些細な発言によって生じた誤解が原因だったようです。私の口から二人に事情を説明して納得してもらい、長い間ギスギスしていたゼミ内の空気がようやく和らぎました。ゼミのメンバーたちによると、私の「親身に話を聞く姿勢」と「言葉を選んだ伝え方」によって、喧嘩を終わらせることができたと言います。
④ビジネスの場でも、一人一人の意見を尊重しながらチームワークを築き、最大限のパフォーマンスを発揮していきたいです。
①結論
結論には、自分の強みを一言で簡潔に書きましょう。この例文では、多少冗長な部分があるため、より簡潔に言い換えることを検討してください。例えば、「気遣いができる」「傾聴力がある」「誰とでも良好な関係を築ける」など、自分に合った表現を選びましょう。
自分の強みについて書く場合、このほかにも「努力し続けられる(継続力がある)」「納得いくまで考える」「物事を慎重に進める(確認を怠らない)」「柔軟性がある(臨機応変に対応できる)」など、さまざまな強みについて書くことができます。ただし、この時に気を付けてもらいたいのが、“仕事に生かせる強み”であるかどうかです。
②理由
①で述べた結論(強み)を裏付ける理由を述べましょう。③で具体的なエピソードの紹介に入るため、ここでは一言で分かりやすく伝えることが大事です。ゼミでの出来事なのか、サークルなのか、アルバイトなのか・・・あなたの強みがどんな時に生かされたのかについて触れましょう。
③具体例
具体的なエピソードを紹介していきましょう。「どんな出来事が起こったのか」「あなたが取った行動は」「どんな結果をもたらしたのか」、読み手に状況が伝わるように書きましょう。その時に工夫したことや、具体的な数字・データ、人から言われた言葉などがあると、より説得力のある文章になります。
④まとめ
自分の強みを会社でどのように生かすことができるのか、今後さらにどのように成長していきたいのか、採用担当者にアピールしましょう。
【例文】長所・短所
【例文】
①私の長所は計画性と行動力です。
②学生時代、学園祭の実行委員を務めた経験があり、そこで長所を発揮することができました。
③半年前から始まった学園祭の準備では、まず私たち実行委員で目標を立て、達成に向けた具体的な計画を立案しました。立案した計画に従って、委員会ごとに役割分担をし、こまめに進捗状況を共有しながら着実に作業を進めていきました。当日は出店数が例年を上回る100を超え、来場者数も過去最高を記録する大成功を収めることができました。実行委員長からは「しっかりとした計画運営が成功の鍵だった」と評価されました。
④入社後もこの長所を活かし、業務の中で目標達成に向けて着実に取り組んでいきたいと考えています。 一方で
⑤細かいところまで行き届かずにいい加減になりがちな面も私には短所としてあります。
⑥大学時代、研究会の新歓ビラを作成する作業を任されたことがありました。期限ぎりぎりまでずるずる先延ばしにし、最終的には間に合わせるために深夜徹夜での作業となり、いい加減な出来で済ませてしまいました。
⑦しかし、この経験を機に自分の甘さに気づき、「やらされ仕事でなく自分の仕事として真剣に取り組む」大切さを学びました。入社後は常に緊張感を持ち続け、計画性と行動力を発揮しつつ、細かいところまでもこなせるよう自分を厳しく律していきたいと考えています。
①結論
私の長所を簡潔に「計画性と行動力です」のように一言で示します。複数の長所がある場合は、主要なものに絞ります。
②理由
その長所が発揮された状況(学園祭の実行委員を務めたなど)を簡潔に説明します。長所が生かされたエピソードの背景を簡単に示します。
③具体例
長所がどのように発揮されたのか、具体的な行動内容(計画立案、進捗管理、役割分担など)とその結果(目標達成、成功例など)を詳しく書きます。第三者からの評価なども添えます。
④まとめ
③で示した長所を、今後入社してからどのように活かし、会社にどう貢献できるかを明確に述べます。
⑤結論
私の短所を「細かいところが行き届かないことです」など、簡潔に示します。長所ほど強調しすぎる必要はありません。
⑥具体例
その短所がどのように表れたのかを、実際のエピソード(新歓ビラ作成の失敗など)を挙げて具体的に説明します。短所のエピソードはあまり致命的なものにならないようにしましょう。例えば、大勢の人に多大な迷惑をかけたエピソードなどは実際そのようなことがあったとしても、書かないようにしてくださいね
⑦まとめ
⑥の経験から学んだ教訓を書き、今後どう克服し改善していくのかを示します。前向きな姿勢を心がけます。
【例文】学生時代に力を入れてきたこと(ガクチカ)
①私は大学時代に空手を頑張りました。
②運動未経験でしたが友人に誘われて入部し、練習を重ねるうちに心身共に強くなっていく感覚が心地よく、引退まで続けることができました。
③入部直後は練習メニューについていけず、私のせいで練習が中断してしまうことも多々ありました。悔しさと申し訳なさから、退部を考えたこともありましたが、これまで何かをやり遂げた経験がなかったため、引退までは続けるという目標を立てました。
④1年生の夏からは毎朝、ランニングと蹴り・突きの練習に励みました。時間に余裕のある日は一般の道場に通い、師範に積極的にアドバイスを求めました。
⑤その結果、部活のメニューについていけるようになるだけでなく、大会で入賞できるまで上達しました。
⑥自主トレを3年生の冬の引退までほぼ毎日続けてこれたことが大きな自信となっています。空手を始める前よりも、「自分には無理だ」と最初から諦めることが減り、積極的になったと思います。
部活やサークルで役職を持っていた人や、大会で優勝したことがある人たちにありがちなのが、「肩書きや成果に頼りすぎてしまう」ことです。ガクチカで企業が学生に聞きたいことは、成し遂げたことの大きさではなく、
「どんなプロセスで目標を達成できたのか、困難を乗り越えることができたのか」
「経験を通して何を得られたのか」
「会社でどのように生かしていけそうか」
ということ。これを踏まえ、以下の構成を意識して書いてみましょう。
①結論
結論には、学生時代に何を頑張ったのかについて書きましょう。質問では“学生時代”と書かれていることが多いですが、中学や高校ではなく、大学時代に頑張ったことを書きましょう。もちろん、中学・高校から大学まで継続的に頑張ってきたことについては問題ありません。
②理由
①を頑張り続けることができたきっかけや、①を始めることになったきっかけについて、端的に述べましょう。きっかけをより具体的に記載する事が面接官の心を掴むきっかけとなります。
③具体例
①に打ち込む中で、印象的だったエピソードを紹介し、具体性を持たせます。苦労を乗り越えた経験や、努力によって成功を収めた経験など、人間的な成長につながった経験が最適です。
④対策
③で紹介したエピソードの中で、ぶつかった課題や、掲げた目標に対して、どのような対策を取ったのかについて書きます。自己PRの「③具体例」同様に、工夫したことや、数字・データ、人から掛けられた言葉などを示すと、読み手に状況がより伝わりやすくなります。
⑤結果
④の対策に取り組んだことで、どのような結果に終わったのかを書きます。
⑥学び
①に打ち込んだ経験から、何を学んだのか、どのようなことに気づいたのか、人間的に成長できた点を書いて文章を締めます。まだまだ課題が残されている場合は、どのように改善していくのかを述べても良いでしょう。
【例文】志望動機
①私は住宅営業を通して、大好きな地元に恩返しをしていきたいと考えています。
②私は貴社で設計・施工して頂いた木造住宅で育ちました。9歳の頃に古い社宅から移り、爽やかな木の香り、床と天井に見られる美しい木目、新しい家に初めて足を踏み入れた時の感動は今でも忘れられません。
③また、貴社の住宅には地元産のスギやヒノキが多く使われており、こうした取り組みは、地元の林業を支え、森林の循環・保全にも繋がります。このため、貴社の木造住宅を広く提供していくことが、地域貢献にもつながると考えました。
④私は人の意見を聞き、それをもとにより良いアイデアを提案することが得意です。お客様の要望に寄り添いながら、人にも環境にも優しい住宅を街に増やしていきたいです。
①主張
最初に、応募先企業でやりたい仕事や目標などを明言します。「知見を広げたい」「大好きな商品に携わりたい」といった、自分中心の目標はNG。会社や社会への貢献意欲をアピールしましょう。この例は企業の商品愛から発想を広げ「地元への貢献」について述べているので、採用担当者にも伝わりやすいはずです。
②理由
①応募先企業や業界に興味を持った理由を、具体的なエピソードとともに紹介していきます。その会社の商品、サービス、取り組みに対し、どのような感想を持ったのかを伝えましょう。
③企業や業界に関する知識
自分がその企業や業界について、きちんと調べていることをアピールすれば印象アップにつながります。大学の授業で学んだことや、企業研究・業界研究で調べた成果について書きましょう。ただし、調べたことをダラダラと羅列するのではなく、自分の考えや主張と絡めて書きましょう。
④まとめ
自分の熱意や強みを活かし、どのように会社に貢献していきたいのか抱負を述べて、文章を締めくくりましょう。
挫折と克服
【例文】
① 私が挫折を乗り越えた経験は、大学3年生の時の起業チャレンジです。
②友人とアプリ開発に取り組んでいましたが、開発の難しさに直面し、挫折しかけました。
③当初、私たちはアプリ開発の経験がまったくなく、プログラミング言語の習得から始めました。しかし、想像以上に難しく、納期にも遅れが生じ始めました。開発費用も予算オーバーとなり、「挫折してもいいのでは」と弱気になりかけた時期もありました。 そんな中、最後の望みとしてメンターにアドバイスを求めたところ、「目的を明確にすれば道は開ける」とエールをいただきました。私たちは改めてアプリのコンセプトを見直し、ターゲットと機能を明確にして開発に取り組み直しました。結果として開発は大変でしたが、リリースすることができました。
④この経験から、何事にも「目的意識を持ち続けること」の大切さを学びました。挫折しかけた時にメンターに助言を求めたことで、新たな視点を得ることができました。私はこの学びを糧に、入社後も目的を見失うことなく、粘り強く取り組んでいきます。
①結論
挫折を乗り越えた経験について簡潔に示します。
②理由
その経験の背景を説明します。
③具体例
具体的にどのような挫折があり、どんな状況だったかを詳しく述べます。 また、その挫折をどう乗り越えたかを書きます。第三者の助言なども含めるとよいでしょう。
④まとめ
その経験から得た学びを書き、今後どう活かしていくかをアピールします。
まとめ
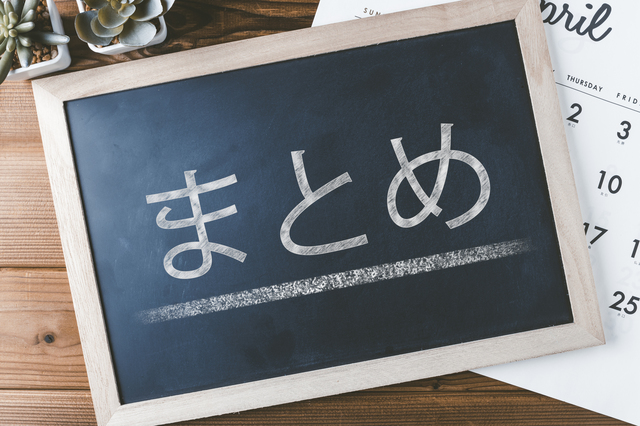
エントリーシートはあなたの第一印象を企業に伝える大切な機会です。適切なエピソードを選び、論理的な構成で書くことで、自分の人となりや能力を効果的にアピールできます。
エントリーシートの内容を作成する過程自体が、自己を見つめ直す良い機会になります。自分自身の強みや可能性に気づき、志望動機をより明確にすることができるでしょう。
入社後の活躍を見据え、熱意と情熱を持って取り組みましょう。企業の求める人材像とマッチした内容を心がけることで、必ず良い評価が得られるはずです。エントリーシートを通して、あなたの人柄が採用担当者に伝わることを期待しています。
スカウト型サイト「就活応縁くまもと」は企業の情報が盛りだくさん!
「就活応縁くまもと(しゅーくま)」は熊本県に特化したスカウト型就活サイトです。地元での採用に力を入れている企業が数多く登録しています。各企業のページには、業務内容や取り組み、採用などに関する情報がたくさん掲載されています。エントリーシートを書く時のヒントが見つかるかもしれません!
しゅーくまの特徴はなんといっても、スカウト機能です。
プロフィールを登録すれば、あとは企業からのアプローチを待つだけでなので、就活の手間を省けます。
企業からのスカウトを承認することで、求人についての質問やインターンシップ参加の日程調整など、直接企業と話しすることもできます。
「熊本が大好きだ!」「熊本のために働きたい!」という学生のみなさん、ぜひ「しゅーくま」を活用して地元での就活をスムーズに進めましょう!