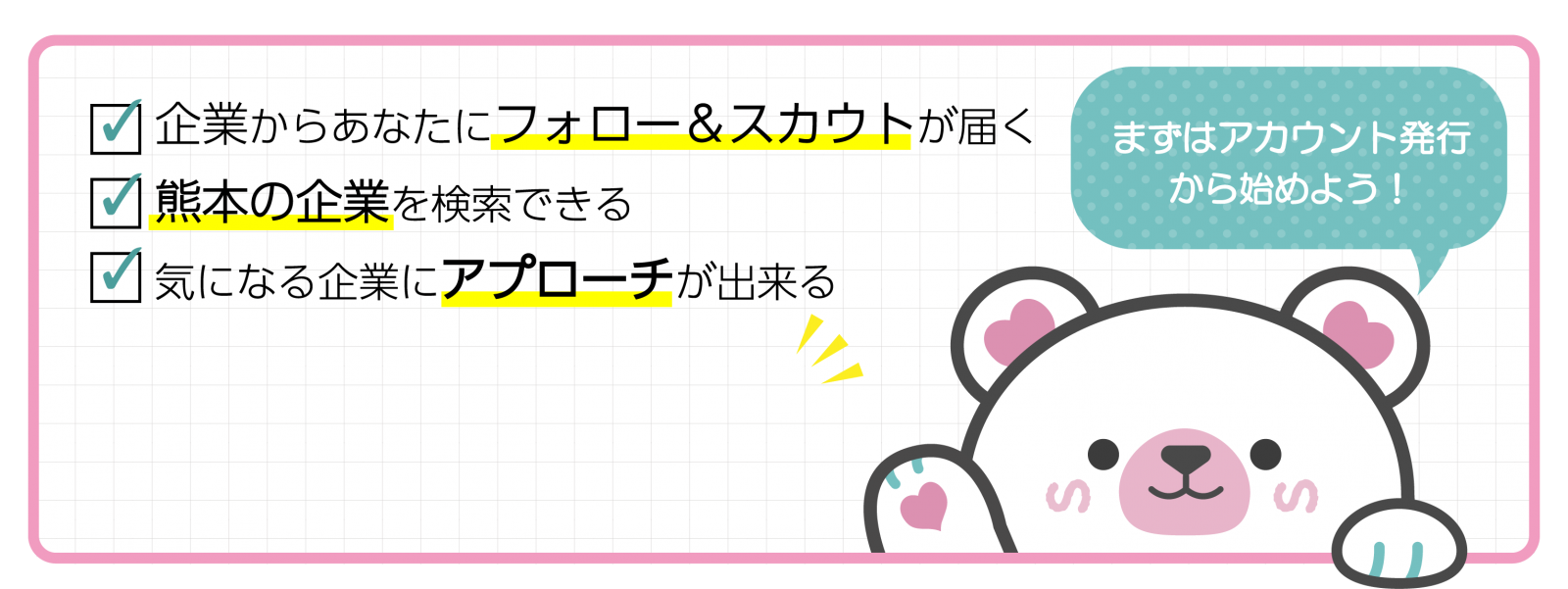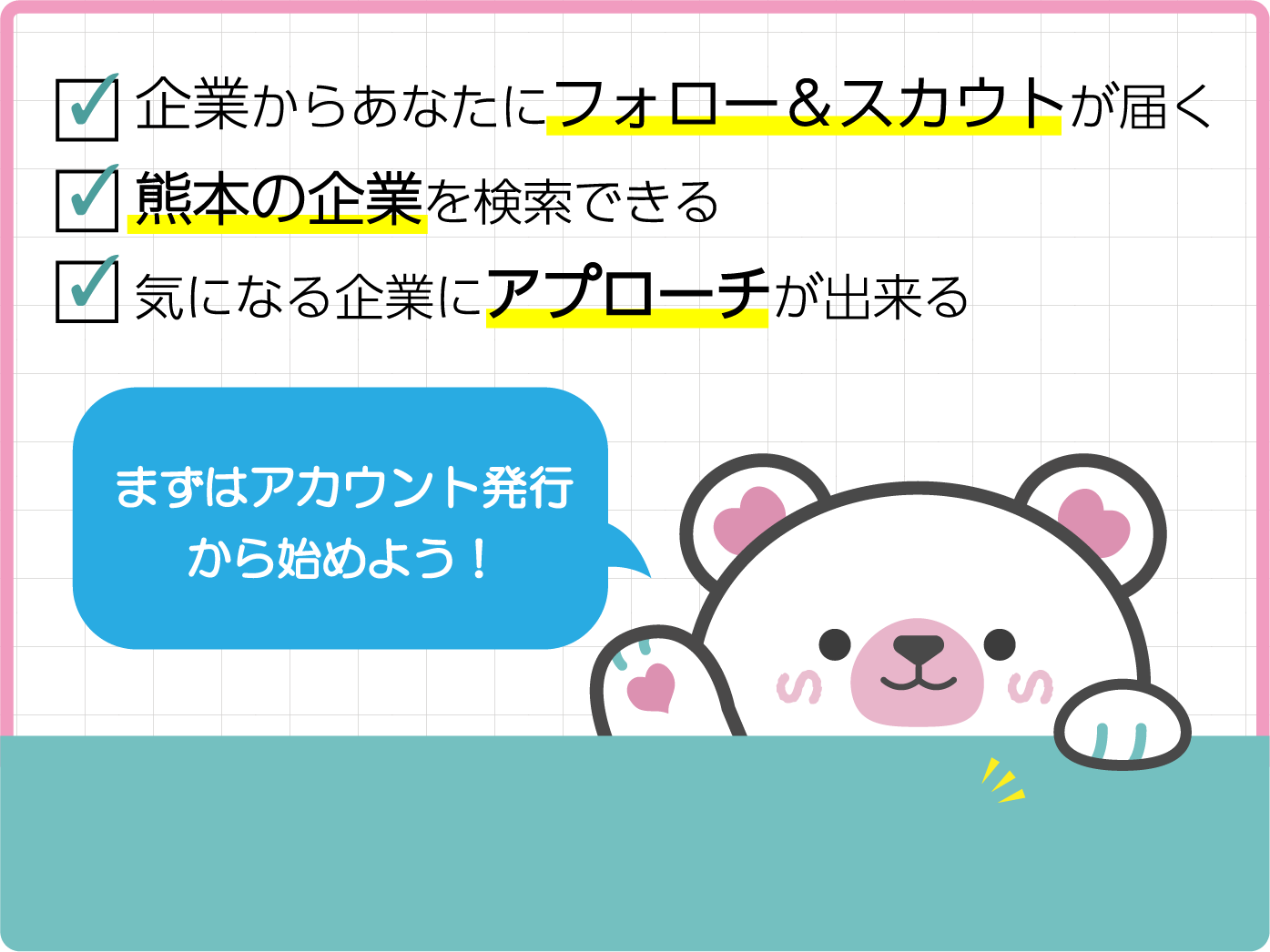様々な企業で実施されている「グループワーク」。
「初対面の人と話すのが苦手」「どのように進めていくのか分からない」「どんな点が評価されるの?」など、不安に思っている人も多いのではないでしょうか。
今回はグループワークの種類や参加者の役割分担、苦手意識を克服する方法などを紹介します
1. グループワークとは?
2. グループワークの種類
3. グループワークの流れ
4. グループワークの役割
5.グループワークで人事は何を見ている?
6.グループワークに苦手意識を持っている人は多い!その理由と対策方法
5. まとめ
6. 熊本で就職するなら「就活応縁くまもと」
グループワークとは?

グループワークとは、グループで与えられたテーマについて議論し、成果物を作って発表することです。企業の選考だけではなく、学校の授業にも用いられます。
グループディスカッションとの違い
グループワークと似た言葉にグループディスカッションがあります。
混同しがちですが、正確には違いがあります。
「グループディスカッション」
与えられたテーマに沿ってグループで話し合い、結論をだします。課題解決型のテーマから、価値観を問うようなテーマもよく出題されます。正解のないテーマは、どれだけ発想力があるかがポイントになってきます。
グループディスカッションのテーマの例
「潰れそうな飲食店に客を集めるには?」
「女性と男性、どちらが幸福か?」
「グループワーク」
グループディスカッションと、ワーク(共同作業)を行います。成果物を作成する過程が
加わるイメージです。
グループワークのテーマの例
「30枚のA4サイズの紙を用いて、高さのあるタワーを作る」
「ジェスチャーのみで誕生日の早い人から一列に並ぶ」
ただ、共同作業があるものをグループディスカッションと呼んだり、企業によって呼び方が異なる可能性もあります。
しかし、グループディスカッションもグループワークも面接官に見られるポイントは同じなので、どちらであってもいいように準備しておきましょう。
グループワークの種類

グループワークは主に「プレゼンテーション型」「ビジネスケース型」「作業型」「ゲーム型」の4種類に分けることができます。それぞれ見ていきましょう。
プレゼンテーション型
プレゼンテーション型は最終的にプレゼンテーションを行うグループワークです。
与えられたテーマに沿って話し合いを行い、それをまとめてプレゼンを行います。
作業系のグループワークは成果物より、その過程が評価の対象になりやすいですが、プレゼンテーション型はプレゼンの出来が評価に繋がりやすいです。
ビジネスケース型
ビジネスケース型は、ビジネスをテーマにグループワークをします。プレゼンテーション型と同様に最終的に意見をまとめてプレゼンを行います。
実際に自社で起きる可能性のある問題など、現場に近い課題について議論することが多いです。企業の情報を調べておくことで、ビジネスケース型のグループワークで役に立つでしょう。
作業型
作業型は、話し合いながらグループで協力し、成果物を作成することです。
新製品のチラシを作成する、画用紙を使ってできるだけ高いペーパータワーを作る、ホームページのリニューアルデザイン案を作るなど、テーマは多岐に渡ります。
作業時間内に成果物を完成させる必要があり、円滑なコミュニケーションや時間配分管理など、参加者が自分の強みをアピールすることができます。
ゲーム型
ゲーム型のグループワークは、ゲーム形式で行われます。ゲーム型のグループワークはゲームの勝敗ではなくその過程が評価対象になります。
グループ内でのコミュニケーションに加え、自分が置かれた状況を判断し対応するなど、柔軟性と発想力が求められます、
グループワークの流れ

グループワークは、最終的な成果物だけでなくそこまでの過程も評価の対象です。
個人が勝手に話を進めてしまっては、スムーズに議論を進めることはできません。グループ全員が一丸となって最終的な結論を出すには、グループワークの流れを意識し、効率的に議論を進めていく必要があります。
役割分担
限られた時間内で効率的に議論を進めるために、役割分担を行います。
具体的な役割は後ほど解説しますが、リーダーになっても役割を持たなくても、評価が左右することはほとんどありません。
基本的に役割は立候補で決めるとスムーズですが、自分の希望する役割に候補が集中した場合は他の役割を選ぶようにするといいでしょう。
議論の方向性をすりあわせる
役割分担が終わった後は、議論の方向性をチームの中ですりあわせていきましょう。
方向性のすりあわせは、5W1Hの「いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように」から、必要なキーワードを選定しましょう。
例)テーマ「インフルエンサーを起用して、SNSでバズる新しいお菓子を企画する」
・いつ→どのシーズンの商品か
・どこで→販売地域
・誰が→ターゲット層
・何を→具体的なお菓子の種類、ターゲット層に合わせたインフルエンサーの提案など
・どのように→販売する場所など
出されているテーマをどのように解決していくかを最初に決めておくことで、議論が拡散せず効率的に進めることができます。
意見を出し合う
役割分担やテーマの方向性が決まったら、意見を出し合います。
意見を出し合う際に注意したいことは、発言していない人をなくすことです。司会になった場合は「順番に意見を出し合いましょう」「○○さんはどう思いますか」など、全員が意見を出せる状態をつくりましょう。
出し合った意見をまとめる
意見を出し合ったあとは、その意見をまとめる作業に入ります。
最初に決めた5W1Hに沿っているかを確認し、必要な意見をピックアップし、テーマに沿っていない意見は排除します。
意見をまとめる際に重要なのは、多数決などで少数派の意見をないがしろにしないことです。
グループ内で「テーマのコストパフォーマンスを重要視する」「問題解決のスピード感を重視する」など判断基準を決めた上で議論を重ね、全員が納得できる結論をだしましょう。
発表
意見がまとまったら、発表の準備をします。より完成度の高い発表にするために、「結論から話す」「話が脱線するようなことは話さない」「ボディランゲージを取り入れる」などの工夫をしましょう。
発表の準備が早く終わった場合はチーム内で発表の練習をすることも重要です。頭で理解していることと、実際に話すことでは違ってきます。
POINT!
詰まることなくスムーズに発表をするために、一回は発表の練習ができるように時間配分をしましょう。
グループワークの役割

グループワークをスムーズに進めるためには、役割分担が重要になってきます。
ここで躓いてしまうと後に響いてくるので、自己紹介をしながら最初の2~3分で早めに役割分担を終えることが大切です。
グループワークの役割は、主に4つに分けられます。
①司会
司会役は、進行役やグループのリーダーの役割を担っています。
司会は限られた時間の中でスピーディーに議論が行えるよう積極性も大切ですが、自分が話すだけでなくグループの全員が話しやすいような雰囲気作りが重要な仕事です。
また、メンバーと意見が食い違っていても感情的にならず、多角的に物事を見る冷静さも必要になってくるでしょう。
②書記
書記はグループワークで出た意見を記録していきます。
意見が多く出ると、一人では記録しきれない場合があるので状況に応じて人数を増やすなどの対策が必要です。
積極的に発言することが苦手な人でも、書記ならチームに貢献することができますが、記録に夢中になりすぎて発言が意見を出すことがおろそかにならないようにしましょう。
③タイムキーパー
タイムキーパーの役割は、名前の通り時間を管理することです。
議論をしていると、想像以上に時間が経つのが早いです。時間制限のあるグループワークでは、議論に時間がかかりすぎてしまうと意見をまとめたり、発表をしたりする時間がなくなってしまいます。
グループワークを発表まで導くために、議論やまとめ、発表準備などの時間配分などのタイムスケジュールを組むこともタイムキーパーの仕事です。
④その他のメンバー
司会や書記などの名前のついた役割がないメンバーも、重要な役割を担っています。
グループワークがスムーズに進行できるように司会に協力したり、良い雰囲気を作ったり、必要があれば書記の手伝いをしたりするといいでしょう。
役割がないから評価されないということはありません。自分ができることを探し積極的にチームに貢献していくことが大切です。
グループワークで人事は何を見ている?

人事から評価されるポイントを理解することで、グループワーク中のアピール力を高めることができます。人事が評価する点は、主に以下の5つです。
①リーダーシップ
リーダーシップといえば「統率力」「指導力」をイメージしますが、リーダーに求められるものはそれだけではありません。
「自分一人でまとめるのではなく、周囲も巻き込んで良い雰囲気をつくる」「メンバーの個性を尊重できる」「具体的な指示を出す」など、様々なタイプのリーダーシップの取り方があります。
自分のできるリーダーシップを実行することで、役割としてのリーダーを担っていなくても、リーダーシップをアピールできます。
②思考力
思考力は情報を集め、自分の頭で考えて判断する、自分の考えを言語化して他者にも意見を求めるなど、誰も正解を教えてくれない状況でも適切に判断し、問題解決に導く力です。
発言力の強い人の意見に流されず、自分の考えを伝えしっかりと受け答えできれば評価ポイントに繋がります。
③協調性
グループワーク中はチームメンバーと協力し、連携して行動できるかどうかが見られています。
入社後は、プロジェクトチームへの参加や売り上げ達成など、ひとつの目標に向かって協力することが求められます。
自分と異なる意見を持つ相手を否定することなく受け入れ、議論をよりよい方向に進めていく姿勢を心がけると協調性があることをアピールすることができます。
④積極性
積極的にグループワークに参加しているかどうかも評価の対象です。
話を振られるまで発言せず受け身の姿勢でいたり、自分の意見を持たず周りに流されたりするだけだと、積極性に欠けると判断されてしまう可能性があります。
自分から発言して議論を進める、自分のできることを探して実行する、初対面の人ともコミュニケーションを取るなどを心がけ、口下手でも議論に関わろうとする姿勢をとることで、積極性を見せることができます。
⑤コミュニケーション能力
自分をアピールするために積極的に発言することに夢中になりすぎて一方的に話してしまったり、逆に人の話を聞いているだけになってしまうと、議論の妨げになってしまったり、チームに迷惑をかけてしまうこともあります。
たくさん発言すればコミュニケーション能力をアピールできるという訳ではなく、話が下手だからといってコミュニケーション能力が低く評価されるという訳でもありません。
コミュニケーション能力は、相手の意見にも耳を傾け、それを尊重しつつ自分の意見を主張する、初対面の人とも話しかけやすい雰囲気を作るなども大切なことです。あまり難しく考えず人を思いやる気持ちを忘れなければ、充分アピールポイントになるでしょう。
グループワークに苦手意識を持っている人は多い!その理由と対策方法

グループワークに苦手意識のある人は多く、グループワークに自信がある人の方が少数派です。グループワークに苦手意識を持つ理由や、その対策方法をまとめました。
人見知りで初対面の人と話せない
人見知りの人は初対面の人の前だとうまく話せない、緊張してしまうということもあって、グループワークに苦手意識を持つことが多いです。
人見知りは、場数を踏むことである程度克服することができます。就活が本格的になる前に、学校の合間に単発でもいいので接客業を体験してみることがおすすめです。
意外と、「顔と名前だけ知ってる人」「一回挨拶した人」より、初対面の人の方が話しやすいという人が多いように、初対面は話題が多く、話が広がるきっかけがたくさんあります。
可能であれば、グループワークが始まる前に同じグループの人に話しかけて、アイスブレイク的なコミュニケーションをとりましょう。事前にどんな人が同じチームにいるかわかれば、落ち着いて話しやすくなります。
自分の意見を話すことが苦手
自分の意見を話すことが苦手な人は「間違った意見を出したら恥ずかしい」「人にどう思われるか心配」と思っているのではないでしょうか?
グループワークは、様々な意見を出し合ってより良い方向に議論を進めることです。
話し合いで自分だけ意見が異なっていても、それは間違いではなく大切な意見のひとつです。
どうしても自分の意見を話すことが苦手な場合、「他人は思っているより自分のことを見ていない」と思いましょう。同じグループのメンバーも、自分のことに精一杯だと考えれば、少しは気が楽になるでしょう。
議論についていける自信が無い
議論についていく自信がない人は、議論についていけないのは自分のせいだと責める傾向があります。
しかし、グループワークでは「議論についていけない個人」より、「議論についていけないメンバーがいるまま議論を進行している」という面をグループ全体の問題として捉えることがあるので、自分を責めすぎないようにしましょう。
議論についていけないときは「今の言ったことを確認してもいいですか?」「ちょっとここが分からないです」など、素直に疑問に思ったことを口に出すことが大切です。
メンバー内で理解できていない人がいる場合、それをふまえて議論を整理し、発表準備を行えるのでよりわかりやすいものになります。
まとめ

会社の仕事は、一人で行うものではなく多くの人と協力し、関わり合って行うものです。
リーダーシップがとれる人、発言が多い人だけが評価されるのではなく、対人関係の中で自分のやるべきことを見つけ、独りよがりにならず、柔軟な発想で着実に目的に向かっていく姿勢が評価に繋がります。
今回紹介した評価される点、グループワークの役割などを理解することで、落ち着いてグループワークに臨むことができるようになるでしょう。
熊本で就職するなら「就活応縁くまもと」
「就活応縁くまもと(しゅーくま)」は、熊本県に特化したスカウト型就活サイトです。地元での採用に力を入れている企業が数多く登録しており、積極的なスカウトが期待できます。各企業の基本情報や採用情報も盛りだくさんなので、必見です。地元企業ばかりなので、勤務地のミスマッチが起こらないことも魅力です。
「しゅーくま」でスカウトを受けると、マイページ内で各企業の担当者と直接メッセージのやり取りができるようになります。求人についての質問や、インターン参加の日程調整などを自由に話すことができるため、その会社をより身近に感じることができるでしょう。
「熊本が大好きだ!」「熊本のために働きたい!」という学生さんは、ぜひ「しゅーくま」を活用して、地元での就活をスムーズに進めましょう!!