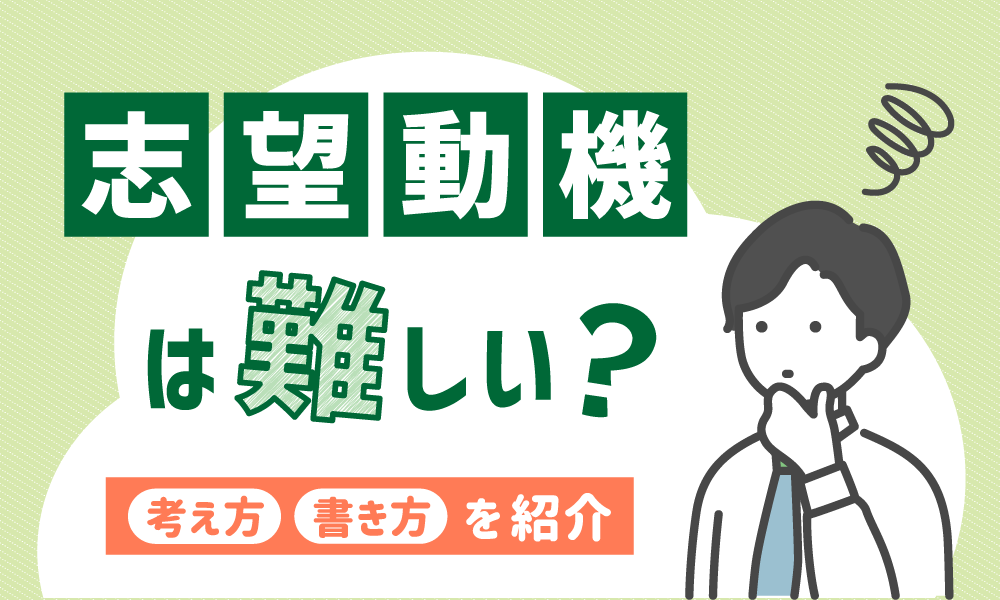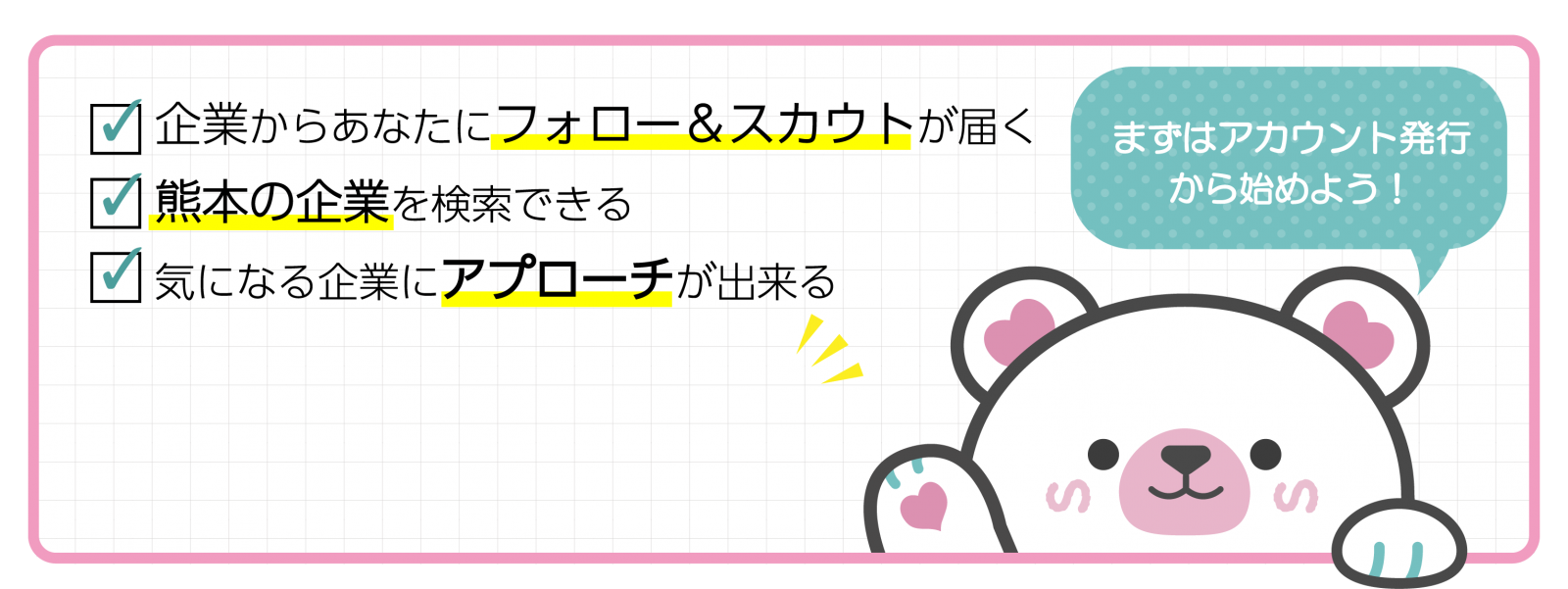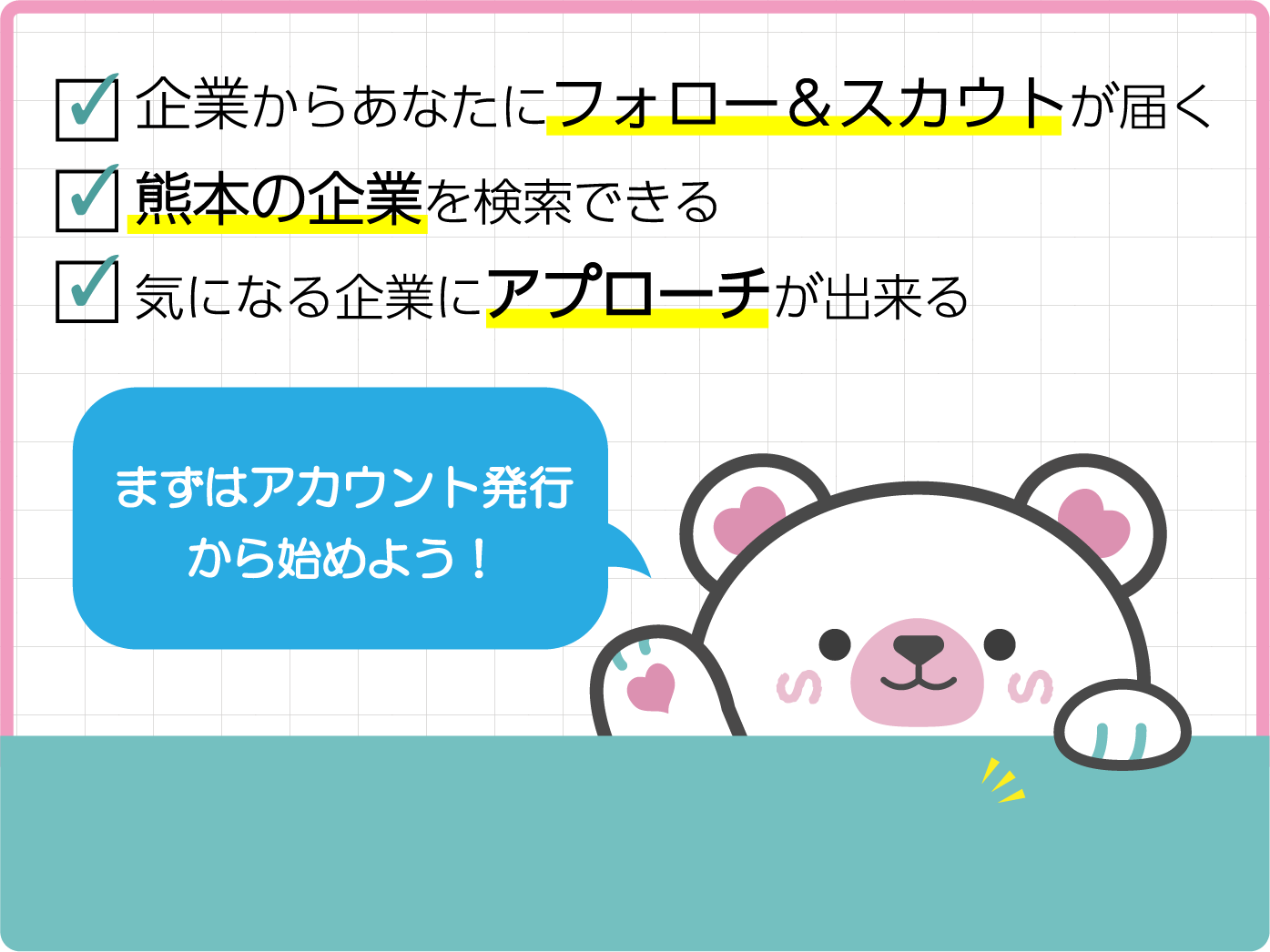新卒の就職活動では、志望動機を書くところでつまずいてしまう方も多いのではないでしょうか?
特に、多くの企業を受けられている方は、企業に合わせて志望動機を考えなければならず、負担に感じることもあるでしょう。
ですが、ポイントを押さえて考えることができれば、難しくありません。
今回は、志望動機の考え方、書き方を紹介します。ぜひ参考にしてくださいね!
2. 企業側は志望動機から何を読み取る?
3. 志望動機はどうやって考える?
4. 志望動機作成につながる企業研究をしよう
5. いよいよ志望動機作成!書き方のポイント
6.志望動機の例文とポイントを紹介
7.まとめ
8. 熊本で就活するなら「就活応縁くまもと」
就活生が志望動機を書きにくいと感じる理由

まず就活生の多くは、なぜ志望動機を書きにくいと感じてしまうのでしょうか?
その原因を探ってみましょう。
複数の企業に応募しているから
一般的に就活生は、複数の企業に幅広く応募することを推奨されます。
何十社も受けている就活生も少なくありません。
受ける企業の数が増えれば、必要な志望動機の数も増えてきます。
ただでさえ忙しいのに、応募企業ごとに志望動機を考えるのは、時間も労力もかかるでしょう。
「A社とB社で矛盾したことを書いてしまった」「心にもないことを書いてしまった」という罪悪感が生まれてしまうのも、考えにくさの一つです。
就活して初めて出会った企業だから
何十社も企業を受けていると、就活で初めて名前を知った、という企業も多いと思います。
「小さい頃から志望企業の製品を使っていた」など、思い入れのある企業ばかりではないはずです。そのような企業の志望動機を深く考えることに負担を感じることもあるでしょう。
業務経験がなく、働くイメージが沸きにくいから
新卒の学生は実際の職務経験が少ないため、特定の業種や職種で働く具体的なイメージが持ちにくいです。
配属によって仕事内容も変わってくるので、「こんな仕事がしたい」と言いにくいのも悩みどころです。
企業側は志望動機から何を読み取る?

企業側は就活生が上記の悩みを持っていることを、十分承知しています。
それでもなお、志望動機について尋ねるのは以下のような理由があります。
企業側の事情を知ることで、志望動機をどう考えるべきか、おのずと明らかになるでしょう。
企業にマッチする(=長く働いてくれる)かどうか
企業が一番意識しているのは、「目の前の学生が企業にマッチして長く働いてくれるかどうか」です。
企業は、新卒の就活生を採用した後、多大なコストをかけて研修・育成を行います。
自社で長く活躍して、利益をもたらす人材になってほしいと考えるのは当然のことです。
就活生の志望動機は、企業にマッチするかどうかの大きなヒントになります。
具体的には、自社への志望度の高さ、納得できる説明か、説明に一貫性があるか、などの視点を重視します。
就活生自身の価値観
また、自社の方向性と就活生の価値観がマッチしているかも大事なポイントです。
企業には、事業を通じて目指す方向や大事にしたい価値観があります。
それは、「企業理念」や「ミッション&バリュー」で示されています。
たとえば、カフェで知られるスターバックス社のミッションは以下のものです。
ーひとりのお客様、一杯のコーヒー、そして一つのコミュニティから
スターバックスカフェを利用している人は、居心地の良さや接客の素晴らしさを感じることもあるのではないでしょうか?同社では、ミッションが社員のみならずアルバイトにも浸透していることで知られているのです。
このように企業は、社員一人一人が同じ方向性で働くことを望みます。
そのため、学生の価値観も、企業の今後の方向性に合うかどうかを重視するのです。
志望動機からは、就活生が企業のどの点を魅力と感じているかが伺えます。
就活生が魅力に感じる点から、学生が大事にしている価値観を探ることができるのです。
志望動機はどうやって考える?

企業側の思いを踏まえて、実際に志望動機を考えてみましょう。
大切なことは、志望動機が企業からどう見えるか?という視点です。
志望動機≠応募のきっかけ
志望動機を考える上でつまずきやすいポイントは、志望動機を応募のきっかけと同一視してしまうことです。
志望動機は、応募のきっかけとは別に考えてください。
例えば、求人サイトで「初任給が30万円!」という文言を魅力に感じて応募したとします。
それで応募すること自体は問題ありません。
多くの人に応募して欲しくてそのキャッチコピーを掲載しているでしょう。
ですが、その応募のきっかけを深掘りしてもあまり意味がないことに気づくのではないでしょうか?
企業側から見ても、初任給30万円ということにのみ魅力を感じている人が、長く働いてくれるとも思わないでしょう。
他にも、応募のきっかけが「家から近い」「社員食堂が充実している」「福利厚生がいい」など、個人的な好みである場合は、企業研究によって本質的な企業像を明らかにする必要があります。
詳細な企業研究の方法は後述します。
自分が企業に対し「何ができるか?」という視点で考える
もう一つ、志望動機を考える際に陥りやすいのが、自分の視点のみで考えてしまうことです。
今までの人生で、大学や部活など、動機を持って行動したこともあるでしょう。
「自分がしたいから」という視点であったことも多いかと思います。
自分のしたいことをするのは人生においてとても大事なことです。
ただ、就職活動においては、自分視点に加えて「企業に対してどう役に立ちたいのか?」という視点を付け加えてみてください。
例えば、「小さい頃から知っている憧れのあの企業で働きたい」という思いを伝えても良いですが、それだけでは企業側にとって、活躍するイメージが沸きにくいです。
「その企業に対して自分は何ができる」「企業の未来のためにこんなことがしたい」という思いを付け加えて話さなければなりません。
そのためには、企業の表面的な理解ではなく、本質的な企業の研究をする必要があるのです。
業界への志望動機、企業への志望動機の2軸で考える
志望動機は、一貫性を持たせることで説得力があるとみなされます。
一貫性を持たせるには、「業界への志望動機」「企業への志望動機」の2軸で考えることが必要です。
業界への志望動機があれば、やみくもに企業を受けているわけではなく、業界研究を行った上で応募していることを示すことができます。
また、その中の企業への志望動機で、業界内の立ち位置や他社との違いなどを理解していることがわかります。
志望動機作成につながる企業研究をしよう

これまで述べてきたように、企業研究こそが、志望動機作成で重要になります。
ただ、何十社も企業を受けている就活生の皆さんは、1社1社について深く企業研究をするのは大変なことです。志望動機作成に必要なポイントを以下紹介します。
企業研究で重点的に見るべき所
志望動機を書く上での企業研究は以下のポイントを押さえておくと良いでしょう。
■ホームページ
・理念/ミッションバリュー:企業が大切にしていることがわかります。
・沿革:その企業の成り立ちにあたっての思いが見えます。
・IR情報:細かい数字よりも、今後の取り組みなどをチェックしましょう。
■業界地図
・業界での立ち位置:業界何位かだけではなく、その企業の個性や特色もわかります。
■Webサイト、新聞
・ニュース:企業の最新の取り組みが書かれています。
最終的に「理念/ミッションバリューに共感した」という志望動機になるとしても、理念に基づいてどんなことをしているか?の取り組みや特色をIR情報で知っておきましょう。事実を知っておくことは、他の就活生と差がつけられるポイントです。
社員の話から聞くべき所
企業によっては、OB・OG訪問や会社説明会など、社員の話が聞ける機会があるはずです。
実際に働いている人の声は、大きな志望動機へのヒントになります。
以下のような事項を聞いてみると良いでしょう。
■社員が働く上で大切にしていること:
「企業が掲げるビジョンや理念と同じ方向性で働いている」「お客様に新しい視点を提供する」など
■社員がやりがいに感じていること:
「お客様のコストを削減できたとき」など
■組織風土:
「新人でも上長に改善案を提案できる雰囲気」など
■評価の方法:
「頑張れば年数に関係なく評価される環境」など
■成長環境:
「新人でも裁量権が大きい」「大きい仕事も任せてもらえる」など
自分自身の取り組みとマッチする部分を見つける
上記の情報を集めたら、自分自身が今まで行ってきた取り組みとマッチしそうな部分を合わせてみましょう。
企業側が知りたいのは、「自社の〇〇な部分を魅力に感じる就活生はどんな価値観を持っているか」だからです。
例えば、以下のようなことを考えると良いでしょう。
・理念:新しい価値を創造していく→自分の大学時代に行った新しい取り組みとマッチ
・OBが述べたやりがい:「お客様に感謝されたことが一番の喜び」→自分が感謝を受けたエピソードに合っている
上記のように、自分の過去の取り組みから、合いそうなものを見つけてみましょう。
いよいよ志望動機作成!書き方のポイント

いよいよ志望動機作成を行います。
ここでは、エントリーシートでの書き方のポイントをお伝えします。
構成の目安は「企業の魅力3割+自分の価値観7割」
構成の目安は、企業の魅力3割+自分の価値観7割です。
企業側は志望動機を通じて、就活生の価値観を重視しています。
そのため、自分の経験を通じた価値観を述べることを中心に書きます。
書き方の順番は?
企業の人事は、莫大な数のエントリーシートを読まなければなりません。
そのため、簡潔で読みやすい志望動機が求められます。
ポイントは、結論を最初に述べることです。
その次に、理由として自分の経験談を展開します。最後は、自分が企業に何ができるかを示すことで締めくくりましょう。
例えば、以下のような型を作っておくことがおすすめです。
自分の経験談「私は学生時代〇〇でした」
経験の総括「このような経験から〇〇ということを学びました」
まとめ「私は〇〇を生かして、御社〇〇がしたいと考えています。」
志望動機の例文とポイントを紹介
では、実際の志望動機の例文を紹介します。
(例1)企業研究から志望動機を作成した場合
まず、企業研究から志望動機を作成した場合の例です。
新卒の場合、「企業理念の共感」が志望理由として多いですが、抽象的になりがちなのも事実です。自分の実体験や行動を述べることで、具体性を強化しています。
私は、貴社の「住居を通じて〇〇県を盛り上げる」という理念に強く共感し、志望するに至りました。
私自身、〇〇県の出身で、この地への深い愛着を持っています。しかし、大学で県外に出た際、〇〇県の魅力が十分に知られていないことに気づきました。そこで私は、〇〇県人会に参加し、文化祭では県外には知られていない名物を紹介するカフェを企画しました。この取り組みを通じて、多くの人に〇〇県の魅力を伝えることができました。ですが、〇〇県の良さ、人の温かさは、住んでこそ実感できるものだと考えています。
また、地方への移住ブームは、自然豊かな〇〇県にも影響を及ぼしていると思います。貴社は〇〇県の総合不動産業として、地域に根ざした魅力を伝える豊富な経験とノウハウをお持ちだと認識しています。
私は、貴社での勤務を通じて、移住者にとって「移住して良かった」と思えるような素晴らしい物件の提供に貢献したいと考えております。
(例2)OB/OG訪問の内容から志望動機を作成した場合
次に、OB訪問から志望動機を作成した場合の例をお伝えします。
実際の社員の話を聞いたという事実だけでも志望度の高さを示すことができます。
それに、自分の行動したエピソードが加わることで、より説得力のある志望動機となるでしょう。
(資材を扱う商社に応募する場合)
私は、貴社の社員の方から伺った組織風土に魅力を感じ、志望させていただきます。
具体的には、新入社員であっても、お客様への改善提案が可能な、風通しの良い環境が魅力的だと感じました。
大学時代、私はコールセンターでアルバイトを経験しました。この職場では、私のようなアルバイトが提案を行うことは珍しい状況でした。しかし、先輩や社員の方々は非常に話しやすく、積極的なコミュニケーションが可能でした。お客様のフィードバックに基づき、話し方のフォーマットを改善する提案を行ったところ、これが採用されました。この提案は、単なる直感に頼るのではなく、お客様の声を定量的に分析した結果に基づいていました。
貴社は資材の商社として、お客様の状況に合わせた最適な提案が重要であると伺っております。私はこれまでの経験を活かし、お客様に信頼される提案を行い、貴社の成長に貢献したいと考えております。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、志望動機の書き方を紹介しました。
志望動機を書くのに詰まってしまったら、企業研究を行って自分とのマッチする部分を見つけてみてください。
この内容が参考になりましたら幸いです。
熊本で就活するなら「就活応縁くまもと」
もし、熊本で就活をするなら「就活応縁くまもと」をおすすめします。
地域に根差した企業からスカウトが届き、自分では見つけられなかった企業と出会うことができるでしょう。
また、本記事の他にも就活に役立つコラムが満載です
ぜひ登録を検討してみてくださいね。
就活応縁くまもと
「就活応縁くまもと(しゅーくま)」は、熊本県に特化したスカウト型就活サイトです。地元での採用に力を入れている企業が数多く登録しており、積極的なスカウトが期待できます。各企業の基本情報や採用情報も盛りだくさんなので、必見です。地元企業ばかりなので、勤務地のミスマッチが起こらないことも魅力です。
「しゅーくま」でスカウトを受けると、マイページ内で各企業の担当者と直接メッセージのやり取りができるようになります。求人についての質問や、インターン参加の日程調整などを自由に話すことができるため、その会社をより身近に感じることができるでしょう。
「熊本が大好きだ!」「熊本のために働きたい!」という学生さんは、ぜひ「しゅーくま」を活用して、地元での就活をスムーズに進めましょう!!